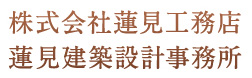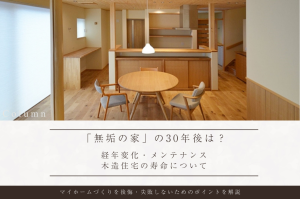木造住宅の寿命と耐用年数の違い|寿命を延ばすための新築・リフォーム・メンテナンスにおけるポイント

これから木造住宅を建てたい方のために、家の平均寿命と期待寿命、耐用年数との違いについて解説します。
家を長持ちさせるために知っておいていただきたい新築時やリフォーム・メンテナンスのポイントも紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。
● 木造住宅は新築時やリフォーム・メンテナンスのポイントを押さえることによって“長寿命化”できます。
● 何十年も安心安全に住める家を建てたい方は、「土地選び・間取りのプラン・住宅性能」にこだわりましょう。
●「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、“手作りの家”をモットーに埼玉県で高性能な住宅を数多く手がけています。
目次
木造住宅の寿命とは|平均年数と期待年数

これから木造住宅を建てる方が気になるのが「家の寿命」ですよね。
国土交通省の調べでは、日本の木造平均寿命(※)は「32.1年」とされており、イギリスの80.6年と比べるとかなり短い年数です。
※木造平均寿命:ここでは、滅失住宅(取り壊される住宅)の平均築後年数とする。
参考:国土交通省|我が国の住宅ストックをめぐる状況について(補足資料)
ただし、近年増えている長期優良住宅(※)は、寿命100年超えも可能とされています。
※長期優良住宅:長期にわたり良好な状態で使用するために、国土交通省が定めた「劣化対策・耐震性・省エネ(断熱性)・維持管理の容易性」などの基準を満たした認定住宅
参考:国土交通省|期待耐用年数の導出及び内外装 設備の更新による価値向上について、国土交通省|長期優良住宅のページ
長期優良住宅は年々増加しており、制度ができた2009(平成21)年から2023(令和5)年までで、累計1,557,320 戸(全体の30%以上)もの戸建住宅が認定を受けています。
参考:国土交通省|長期優良住宅の認定状況について(令和5年度末時点)~新築戸建ての着工戸数に対する割合が31.3%に(4年連続増)~

日本の木造住宅が諸外国より“短命”な理由

近年は長期優良住宅などの高性能住宅が増えたこともあり、住宅の平均寿命は長くなっていますが、まだまだ諸外国と比べると短命と言わざるを得ません。
その理由は主に5つ考えられます。
- 高度成長期(1955〜1973年)に建てられた家は、質があまり良くない住宅が多いため
- 近年まで、住宅性能や品質よりも価格を重視する傾向が強かったため
- 日本では古くから新築住宅を好む文化が根付いており、まだ住める住宅でも建て替えるケースが多かったため
- 税法によって法定耐用年数が定められており、木造住宅の場合は築20年を超えると不動産的資産価値がほぼゼロになるため
- リフォームやリノベーションによる付加価値が中古物件市場において価格に反映しにくいため
これらの理由によって、これまで築30〜40年で家を建て替えるケースが多く、それが家の平均寿命を短くしていた要因とされています。
しかし近年は建築にかかわるコストが高くなった点や住宅建て替えによって多くのエネルギーが消費される点などが懸念され、「新築時に長持ちする家を建てて、世代を超えて住み継ぎたい」という方が増えています。
木造住宅の耐用年数とは|法定・物理的・経済的の違い

「家の寿命=耐用年数」と思うかもしれませんが、耐用年数にはいくつかの種類があり、それぞれ表す意味は異なります。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、固定資産税を算出したり不動産の価値を公平に評価したりするための基準です。
税法上では法定耐用年数を「建物の価値が存続する期間」と定義し、減価償却できる期間としています。
木造住宅の法定耐用年数は居住用(非業務用)が「33年」で、賃貸用などの業務用が「22年」です。
これらの年数を超えると税務上の価値はなくなり、それに伴って中古住宅市場でも価格はかなり下がってしまいます。
経済的耐用年数
経済的耐用年数とは、その建物を売却する際に価値がある(=価格がつく)とみなされる期間を指します。
日本の不動産業界においては原価法(※)をベースに建物の価格を決めるため、法定耐用年数に近づくほど安く見積もられるのが通常です。
※原価法:不動産鑑定における評価方法のうちの1つで、対象不動産の再調達原価を算出し、そこから築年数に応じて減価修正するため、古い家ほど価格が低くなる。
原価法で建物の価値に大きく影響する要素が法定耐用年数で、建物のメンテナンス状態や機能はあまり付加価値になりません。
そのため、築20~25年で木造住宅の不動産価値(売り出し価格)はゼロに近くなるのが現状です。
ただし、人気の高いエリアや建物規模や間取りが一般的なものから逸脱している物件は、築年数が経っていても経済的耐用年数が25年を超える場合もあります。
物理的耐用年数
物理的耐用年数とは、建物構造そのものが物理的に使用できる年数を表し、「寿命」と等しいと言っても間違いありません。
ただし、物理的耐用年数は法定耐用年数のように構造種別ではまとめられず、以下の要素によって変動します。
- 立地環境(土壌や地盤の状態、日当たりなど)
- 気候特性(雨天率や平均気温など)
- 新築時の住宅性能(耐震性や断熱性、その他建築材料のグレード)
- 住宅の管理状況(どこまでメンテナンスが行き届いているか)
住宅性能が全体的に底上げされている昨今において、木造住宅の物理的耐用年数は「50〜80年程度」とされています。
しかし、水捌けや日当たりの悪い土地に建つ家やあまり手入れされていない家は、40年も経たずに建て替えを余儀なくされる可能性は決して低くありません。
木造住宅の寿命を延ばす方法|新築時のコツ

長寿命な家を新築したい方は、7つのポイントを押さえて間取りのプランや建築会社を検討しましょう。
災害リスクの低い土地を選ぶ
地震や台風被害の多い日本においてずっと安心安全に住み続けられる家にするためには、できるだけ災害リスクの低い土地を選ぶ必要があります。
土地を探す場合は、事前にハザードマップを確認しましょう。
ハザードマップでは、地図上で以下のリスクについてレベルを確認できます。
- 洪水
- 内水浸水
- 土砂災害
- 高潮
- 津波
- 液状化現象(※)
※液状化現象:地震の揺れによって土壌に含まれる砂や砂利の結合が解けて、地表付近が液状のようになる現象のこと。液状化が発生すると、上の建物が沈下するなどの被害が出る。
そのほか、場所によっては土地の特徴や成り立ち、地形もチェックできるので、土地の候補が見つかったら、ぜひ一度見てみてください。
適切な地盤改良を実施する
2000年より建築基準法によって建築前の地盤調査が義務付けられていますが、地震に強い家にするためには、調査結果に基づいた適切な地盤改良が必要です。
※参考:建築基準法施行令第38・93条
万が一、液状化現象のリスクがある土地でも、地盤改良によって丈夫な家を建てられます。
良質な木材を使用する
木造住宅を長持ちさせるためには、適切な含水率までじっくりと時間をかけて乾燥させた良質な木材を使用しましょう。
JAS(日本農林)規格では含水率18〜20%の木材を乾燥木材の規格としていますが、木材にこだわる場合は「含水率15%」、平均平衡含水率(※)程度の木材がおすすめです。
※平均平衡含水率:木材を放置したときに安定する含水率で、変形リスクが低い。
断熱性・耐震性・更新性にこだわる
住宅性能の高い家は、建物そのものの寿命が長くなるだけではなく、健康面やコスト面においてもメリットがあります。
- 断熱性の高い家は、内部結露が発生しにくく、木材腐朽菌やシロアリが繁殖しにくい(=柱や土台などの構造体が劣化しにくい)
- 断熱性の高い家は、室温が外気温の影響を受けにくく、部屋ごとの温度がムラになりにくい(=健康で快適な生活を実現できる)
- 断熱性の高い家は、空調負荷を抑えられて、光熱費削減になる(=環境にやさしい)
- 耐震性の高い家は地震や台風による建物被害を最小限に抑えられる
- 建物の更新性(メンテナンスやお手入れのしやすさ)が高い家は、劣化を早く見つけられてすぐに対処できる(=リフォーム費用の削減や建物の長寿命化につながる)
これらの条件を全て満たすと、長期優良住宅として認定を受けられて、ローンの金利や税控除の対象借入上限額が引き下げられたり、地震保険の割引を利用できる可能性があります。
▶︎おすすめコラム:
長期優良住宅の後悔理由と対策|知っておくべきメリット・デメリットを徹底解説
ずっと住み続けられる設計プランにする
長く住み続けられる家にするためには、将来を見越した間取りや、構造部・内外装仕上げ材の物理的な劣化対策が重要になります。
具体的な方法の例は以下のとおりです。
- 近い将来にお子様が独立する場合は、子供部屋を別の用途でも使えるようにする
- 近い将来にお子様が増える場合は、収納スペースを多めにしておく
- 近い将来に車椅子などを使用する可能性がある場合は、玄関を広くしたり寝室を1階に配置して水回りを近くにしたりするなど、バリアフリーも考慮する
- 外壁に直接雨が当たらないように軒の出(※)を深くして、外壁材の劣化を防ぐ
- 水捌けを良くするために屋根の形状をシンプルにして、雨漏りのリスクを抑える
- 屋根の雨樋(横樋)に落ち葉が溜まって排水不良を起こさないように、家の近くに落葉樹を植えない
※軒の出:外壁面から飛び出た屋根の先端(軒先)までの水平距離を意味し、軒裏天井の奥行きを指す。
土地・エリアを知り尽くした会社に相談する
住みたいエリアが決まっている方は、そのエリアや土地の特性を知り尽くした“地元”の建築会社へ相談することをおすすめします。
地元に根付いた設計事務所や工務店は、住み始めてから家に何か不具合があっても、すぐに対応できます。
また、その地域の条例や自治体の補助金制度などに詳しい点もポイントです。
設計施工実績が豊富な会社に相談する
設計施工実績は、建築会社にとって“カタログ”そのものです。
「こんな家を建てたい」とイメージが固まっている方は、それに近い住宅の設計施工実績が豊富な建築会社に相談しましょう。
後悔のない家づくりを実現するためには、いろいろな会社の建築事例を見て理想のイメージを作ることが重要になります。
蓮見工務店はお客様一人一人の理想に寄り添い、注文住宅の新築からリノベーションまで「高いデザイン性と住宅性能」にこだわっています。
雑誌掲載事例も多数ありますので、デザイン・間取り・性能を全て妥協しないマイホームを手に入れたい方は、お気軽にご相談ください。

木造住宅の寿命を延ばす方法|リフォーム・メンテナンスのコツ

木造住宅の寿命を延ばすためには、新築時のポイントだけではなく、リフォームやメンテナンスについても知っておく必要があります。
定期的な点検を徹底する
建物の長寿命化に欠かせないのが「定期点検」です。
- 1〜2年に一回程度のセルフチェック
- 5〜10年に一度程度のプロによるチェック
これらの点検を徹底することで、不具合や劣化サインを早期発見できて雨漏りなど深刻な問題が発生することを未然に防げます。
主なチェックポイントは以下のとおりです。
| セルフチェック | 基礎(割れ・蟻道・不同沈下・欠損など) 外壁(汚れ・色褪せ・塗膜の剥がれやひび・シーリングの劣化など) 屋根(色褪せ・浮き・ずれ・割れなど) 雨樋(詰まり・ずれなど) 軒裏(腐朽・雨漏り・塗膜の剥がれやひびなど) 屋内(床・壁・天井の異変) 建具(窓サッシ・玄関ドアの異変) 設備機器(水漏れ・詰まり・悪臭・シーリングの劣化・作動不良・固定不良など) |
| プロによるチェック | セルフチェックの項目 床下(湿度、基礎からのずれや浮き、断面欠損、腐朽、蟻害など) 床組(腐朽、蟻害、床鳴りなど) 小屋裏(雨漏りの有無など) 給排水管(漏水・赤水・排水不良など) |
年数ごとの点検に加えて、大きな地震や台風の後は臨時に点検をするとさらに安心です。
長期優良住宅は新築時に維持保全計画書を作成することが義務付けられており、それに沿って点検しないと認定が取り消される可能性があるので注意してください。
参考:住宅金融支援機構|入居後の住まいの保守管理|マイホーム点検・補修記録シート
適切な時期にリフォーム・メンテナンスする
家を長持ちさせたい方は、定期点検の結果を踏まえて、適切な時期にリフォームやメンテナンスを実施しましょう。
| 部位 | 改修サイクルの目安と工事内容 |
|---|---|
| 外壁(金属サイディング) | 3〜5年ごとに塗り替え 15〜20年ごとに全面改修 |
| 外壁(窯業サイディング) | 15〜20年ごとに全面改修 |
| 外壁(モルタル塗装) | 15〜20年ごとに塗り替え |
| 屋根(金属系屋根材) | 3〜5年ごとに塗り替え 15〜20年ごとに全面葺き替え |
| 屋根(化粧スレート) | 15〜20年ごとに全面葺き替え |
| 雨樋 | 7〜8年ごとに全面取り換え |
| 軒裏天井 | 15〜20年ごとに全面取り換え |
| 鉄部(屋外) | 3〜5年ごとに塗り替え 10〜15年ごとに全面葺き替え |
| 床組 | 20〜30年ごとに全面取り換え |
| 床下 | 5〜10年ごとに防腐・防蟻処理 |
| フローリング | 6〜25年ごとに全面張り替え |
| 室内木製ドア | 10〜20年ごとに取り換え |
| 窓サッシ 玄関ドア | 15〜30年ごとに取り換え |
| キッチン 洋室 トイレ 換気扇 | 15〜20年ごとに取り換え |
| ガス給湯器 | 10〜15年ごとに全面取り換え |
| 給排水管 ガス管 | 15〜20年ごとに全面取り換え |
参考:住宅金融支援機構|入居後の住まいの保守管理|マイホーム維持管理の目安
ただし、改修サイクルは新築時に設置した材料(機器)のグレードや使用頻度によって変動するため、家を建てた建築会社に定期点検を頼み、リフォームやメンテナンスのアドバイスをもらいましょう。
まとめ

木造住宅の寿命は建築材料や施工方法の進化によって以前よりも延びていますが、新築時やリフォーム・メンテナンスのポイントを押さえることによってさらに“長寿命化”できます。
何十年も安心安全に住める家を建てたい方は、「土地選び・間取りのプラン・住宅性能」にこだわりましょう。
デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、注文住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。