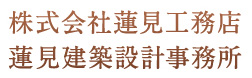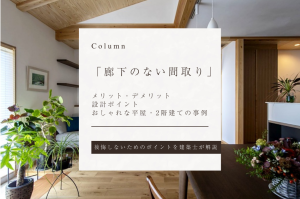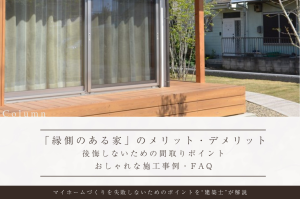「漆喰の家」の後悔理由と対策|メリット・デメリットから見る失敗しないためのコツよくある質問
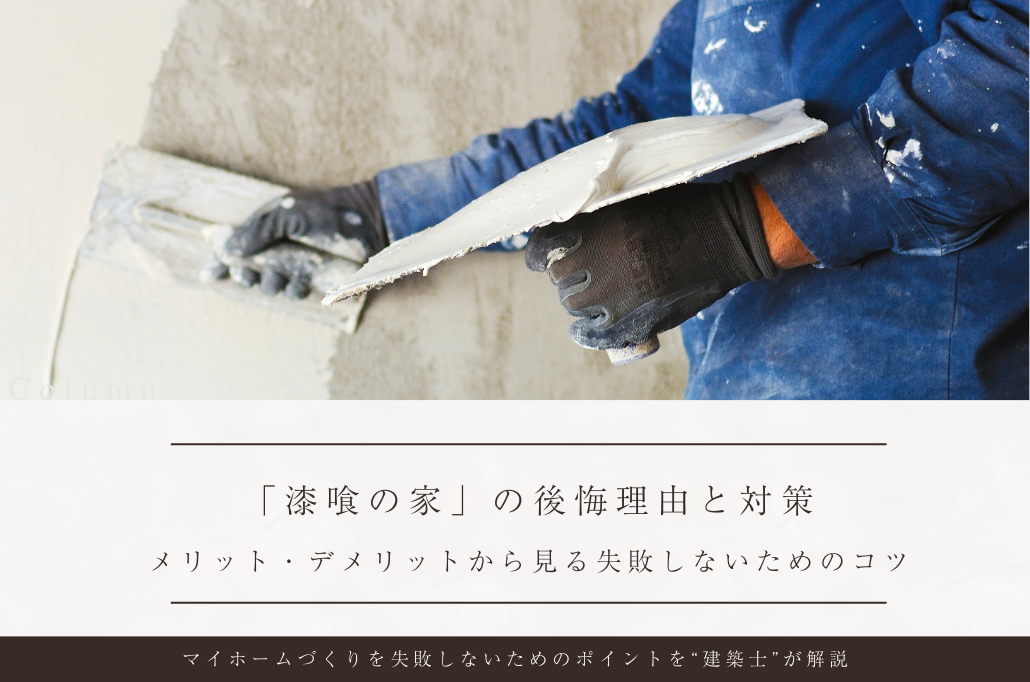
「自然素材にこだわった家を建てたい」「塗り壁の家にしたいが欠点がないか失敗」という方のために、今回は“漆喰の家”を後悔した理由とその対策、メリット・デメリット、その他、耐用年数や断熱性・耐震性など多くの方からいただく質問について詳しく解説します。
蓮見工務店の施工事例を交えてマイホームを後悔しないためのポイントを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
● “漆喰の家”を建てたい方は、コストやメンテナンス方法、耐用年数(寿命)、デザイン性などを総合的に確認して検討する必要があります。
●「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、「手作りの家」をモットーに埼玉県で高性能な住宅を数多く手がけています。
目次
「漆喰の家」とは|漆喰の特性と歴史

“漆喰の家”とは、漆喰を家の内壁や外壁、天井などに仕上げ材として使用する家を指すのが一般的です。
漆喰は消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とする塗り壁材で、砂や繊維、のりなどを混ぜて施工します。
日本において漆喰塗りの歴史は長く、その始まりは平安時代初期の神社仏閣建築とされており、それ以前にも古墳の壁画などに使用された事例は少なくありません。
“漆喰の家”は、一時期、施工効率の良いビニールクロス仕上げの台頭によってその数が減少しましたが、近年は以下の観点から自然素材として選ぶ方が増えています。
- シックハウス症候群※対策
- 環境負荷軽減(塩ビ系素材の使用量削減)
- 設備機器に頼らない調湿効果
- 気候変動による夏季の高温多湿化への対策(調湿効果)
※シックハウス症候群:室内空気環境の悪化により、皮膚・粘膜刺激症状やめまい、嘔気・嘔吐などの症状が起こり、その場所を離れると改善されるものを指し、建築材料に含まれる化学物質(ホルムアルデヒド、VOCなど)や、真菌(かび)、細菌、ダニなどが原因(参考:厚生労働省|科学的根拠に基づく シックハウス症候群に関する 相談マニュアル(改訂新版))

ブログ・SNSで見る「漆喰の家」の後悔理由・デメリット

自然素材の家を建てたい方から人気の高い“漆喰の家”ですが、SNSやブログを見ると住み始めてから「後悔した」「失敗した」という口コミを見かけます。
そこで、よくある後悔の理由とその対策を紹介します。
「材料費と施工費が高くなった」
漆喰塗りは、クロス仕上げや塗装仕上げと比べると材料費・施工費のどちらも高めです。
| 仕上げの種類 | 単価目安 |
|---|---|
| ビニルクロス | 1,000〜2,000円/㎡ ※特殊仕様除く |
| 塗装 | 1,000〜2,500円/㎡ ※特殊仕様除く |
| 漆喰 | 4,000〜8,000円/㎡ |
そのため、家全体を漆喰仕上げにすると、当初の予算からオーバーする可能性があるので注意しましょう。
人が長時間滞在する場所とそうでない場所、人の目に触れない場所などの観点で仕上げ材を検討しましょう。
漆喰塗りはその他の内装仕上げ材よりコストがかかりますが、耐久性が高くやりかえの間隔が長いため、建物のライフサイクルで考えると維持費を抑えられます。
「工期が長引いた」
漆喰などの塗り壁は、クロス仕上げや塗装よりも一日に施工できる面積は少なめです。
養生や下処理、各工程の乾燥、仕上げ、片付けなど全ての工程を含めると、6畳間の壁面(≒20㎡)でも丸1日から2日はかかります。
クロス仕上げや塗装もいくつかの工程が必要ですが、同じ程度の面積であれば1日もかからず施工できるケースは珍しくありません。
各工程の乾燥に時間がかかる寒い冬などには特に注意が必要です。
予算計画と同様に、空間ごとで漆喰・クロス・板張りなど異なる仕上げ材と組み合わせるプランもご検討ください。
「模様替え・リフォームをしにくい」
漆喰は一度塗ると、後から他の素材に変更したり下地から塗り替えるのに時間と手間がかかります。
上塗りする場合を除いて、塗り替えや他の素材に変える際には既存の漆喰を全て除去して下地からやり直す必要があるためです。
漆喰の上に塗装したりクロスを貼ったりできますが、以下の点に注意しましょう。
- 古い漆喰の上にパテ処理してクロスを貼っても、浮いてくる可能性がある
- 上貼りするクロスを長持ちさせるためには、漆喰の上に壁下地(合板や石膏ボード)を上貼りする必要がある
- 壁下地から浮いている漆喰に塗装すると、大きく剥がれ落ちる可能性がある
- 漆喰は強アルカリ性なので、耐アルカリ性塗料でないと塗れない
- 透湿性のある塗料でなければ漆喰の調湿性に追従できない
- 漆喰と塗膜の密着性を高める下塗り・上塗りが必須
こまめに内装をやりかえたい方には、手軽にリフォームできるビニールクロス仕上げや塗装仕上げがおすすめです。
「パターン(模様)がイメージと違う」
漆喰の壁や天井は、ビニールクロスなどの工業製品とは異なり手作業で塗るため、様々なパターンを表現できます。
その反面、施工者の技術力によって仕上がりに差が出る点は否めません。
平滑なフラット仕上げは施工時間がかかり、ムラが目立ちやすいので注意しましょう。
漆喰塗りの主なパターンは以下の通りです。
・コテ波仕上げ
・ハケ引き仕上げ
・コテバケ仕上げ
・扇仕上げ
・スポンジローラー仕上げ
・スタッコ調仕上げ
・ゴムローラー仕上げ
・マーブル仕上げ
「住んでいるうちにヒビ・欠けが目立ってきた」
漆喰は自然素材で空気中の湿気を吸収して抱え込み、乾燥時にはそれを放出します。
この機能を調湿性能と呼び、室内空間を快適な湿度環境に保てる点がポイントです。
しかし、漆喰は乾燥・湿潤に伴って膨張・収縮するため、何もしていない状態でも細かいヒビが入る事例は少なくありません。
また、下地合板と漆喰は膨張率が異なり、追従できずに表面がひび割れる可能性もあります。
経年によるヒビに加えて、壁の出隅などに強い衝撃を受けると、欠けるリスクもあるので注意が必要です。
直射日光の当たる場所は経年によるヒビが入りやすいので、部位ごとに仕上げ材を分ける方法もご検討ください。
物がぶつかりやすい場所には、表面強度が高い板張りがおすすめです。
▶︎おすすめコラム:【建築士解説】無垢材の住宅|デメリットと床・家具・壁・天井に取り入れるための対策
「メンテナンスや修繕に費用がかかる」
漆喰はクロス仕上げや塗装よりも耐用年数が長く、通常の環境ではこまめなメンテナンスが必要ありません。
しかし、欠けやヒビを補修するためにプロに依頼すると、たとえ小さな部分でも費用がかかるので注意しましょう。
小さなヒビやキズ、欠けであれば、補修材を使ってDIYでも修繕できます。
ただし、フラット仕上げでは上塗りした場所が目立つため、こまめに補修したい方は、ランダムなパターン仕上げがおすすめです。
「汚れ・キズ・シミが目立つ・落ちにくい」
漆喰には撥水性がないため、液体が表面に付着すると汚れやシミが付きます。
すぐに固く絞った布巾などで拭き取れば汚れ・シミは薄くなりますが、そのまま放置すると取れなくなるので注意しましょう。
一部のメディアでは、漆喰のシミ・汚れを消しゴムやメラミンスポンジで擦ったり、カッターナイフで表面を削り取ったりする方法が紹介されていますが、その部分だけ色味が変わったりパターンがなくなったりして目立つので要注意です。
そのため、水はね・油はねのリスクが高い水回りに漆喰を採用する場合は、十分にご検討ください。
「画鋲やテープを使うときには注意が必要」
漆喰塗りの壁に画鋲を刺したりテープを貼ったりする際には、“剥がれ”と“跡”に注意しましょう。
- 古い漆喰に画鋲やテープを使うと、漆喰が大きく剥がれる可能性がある
- 比較的新しい漆喰でも、画鋲やテープを使って重いものを吊るすと、ヒビ割れる可能性がある
- 粘着力の高いテープは漆喰表面に跡が残る可能性がある
新築・リフォーム(リノベーション)と合わせて、広い壁にはピクチャーレール※を取り付けておくのもおすすめです。
※ピクチャーレール:壁や天井に取り付けるレールで、ワイヤーやフックと組み合わせると、壁に画鋲・釘・テープを付けずにポスターや絵画を展示できる

「漆喰の家」のメリット・選ばれる理由

“漆喰の家”を後悔している方がいる反面、「選んでよかった」と感じている方は少なくありません。
漆喰には、安心安全な暮らしを実現する上で重要となるメリットがいくつもあります。
「自然素材で化学物質をほとんど放出しない」
漆喰は自然素材であるため、シックハウス症候群の原因となる化学物質の含有量が少ない建築材料です。
そのため、幼児や高齢者、ペットのいる世帯に多く採用されています。
ただし、シックハウス症候群の原因物質には、ホルムアルデヒドなどの化学物質だけではなく、カビ・ダニの死がいやタバコ、粉じん、黄砂なども含まれるため、漆喰だけでは完全に防止できない点にはご注意ください。
(参考:厚生労働省|科学的根拠に基づく シックハウス症候群に関する 相談マニュアル(改訂新版))
「ナチュラルで素朴なデザイン性・職人による匠の技を感じられる高い完成度」
漆喰のマットな風合いと、ハンドメイド感のあるランダムパターンによって、ナチュラルで素朴な印象に仕上がる点も人気の理由です。
家族の思い出づくりとして、漆喰の下地までプロに依頼し、最終塗りを施主様ご自身でやるケースも少なくありません。
一方、フラット仕上では、職人の高度な手作業ならではの、質の高い完成度を実感できます。
「調湿性が高い」
漆喰の原料である消石灰は多孔質構造で、小さな空洞に空気中の水分を抱え込むことができ、乾燥している空気にそれを放出するため、調湿性能があります。
※漆喰は一般的に湿度70%以上で吸湿し、40%以下で放湿します。通常の室内における湿度快適域は40~60%なので、「過剰な湿度上昇を防ぐ」効果として機能します。
調湿性のある材料を内装に採用すると、結露防止やカビ・ダニの繁殖抑制につながる点もポイントです。
ただし、建築材料の性能を客観的に評価するJIS規格(日本産業規格)において、漆喰は調湿建材としての基準を満たしていません。
| JIS規格での調湿性能基準 | 70g/㎡/24h |
| 漆喰の平均的な調湿性能 | 40g/㎡/24h |
そのため、「漆喰を塗ればそれだけで室内の湿度が安定する」という訳ではない点には注意しましょう。
快適な湿度の室内を実現したい方は、同じく調湿性能のある無垢材などと組み合わせるプランがおすすめです。
▶︎おすすめコラム:板張り天井を後悔しないためのコツ|メリット・デメリットと材料、事例を解説
▶︎おすすめコラム:人気の“無垢フローリング”に要注意|デメリット・注意点やその他床材との違いを解説
「消臭効果・抗菌&抗ウイルス効果がある」
漆喰(消石灰)は多孔質構造でさらに強アルカリ性※であるため、細菌やウイルスを不活性化し、臭いの元を吸着して分解する効果があります。
※漆喰のpHは約12.5で、石鹸水よりも高い
また、表面に付いた微生物や有機物の繁殖も抑制するため、それらを栄養源とするカビ・ダニの対策になる点もポイントです。
ただし、経年とともに消石灰が空気中の二酸化炭素(CO2)と反応して中性化して炭酸カルシウムへと変化して抗菌・抗ウイルス効果などは低下するため、機能を維持したい方はコーティング剤を併用する方法がおすすめです。
「防火性が高い」
漆喰は燃えにくく、告示でも不燃材料に認定されています。
そのため、漆喰の壁や天井はそれ自体が燃えにくいだけではなく、周囲への延焼を防ぎ、防炎効果もあります。
また、漆喰は自然素材なので、燃焼時に有害物質が発生しない点もポイントです。
「遮音(吸音)性が高い」
漆喰(消石灰)は、多孔質構造の空洞によって高い遮音・吸音効果を発揮します。
そのため、室内の壁に施工すると外への音漏れを軽減でき、外壁に施工すると騒音対策になります。
ただし、窓面積の多い間取りではガラスも遮音・防音性能にする必要があるので注意が必要です。
「経年変化が少ない・耐久性が高い」
漆喰は、クロス仕上げや塗装と比べて経年変化や経年変色が少ない建築材料です。
また、高耐久な仕上げ材としても知られており、使用環境や塗り厚によっては50年以上メンテナンスが不要な可能性も期待できます。
ただし、直射日光が長時間当たったり雨風にさらされたりする環境下では、剥離やひび割れ、カビ・コケ・藻が発生する場合もあるため、施工範囲は漆喰の採用実績が豊富な建築会社とじっくりご検討ください。
「ホコリがつきにくい」
漆喰はビニルクロスなどとは異なり、静電気を溜め込まないため、空気中を舞うホコリを引き寄せません。
ただし、凸凹が大きいパターンではホコリが引っかかり、さらに拭き掃除しても汚れをきれいに除去しにくいので注意が必要です。
施工事例(作品紹介)のページでは雑誌掲載事例を多数紹介していますので、ぜひご覧ください。

「漆喰の家」に関する“よくある質問”

蓮見工務店はこれまで数多くの“漆喰の家”を手掛けてきた実績があります。
そこで、多くのお客様からいただいた漆喰に関するご質問を紹介します。
Q.「漆喰壁は10年後どうなる?寿命はどのくらい?」
A.「漆喰壁は施工部位により寿命が大きく異なります。」
紫外線・雨風を多く受ける外壁では、10〜20年でひび割れや表面の浮き・剥離が発生する可能性があります。
そのため、漆喰は風通しが良く直射日光の当たりにくい場所におすすめです。
一方、室内壁では、窓辺など直射日光が当たらない限り、簡易的な補修で30〜100年程度機能を維持できる可能性があります。
Q.「漆喰の家は寒いって本当?」
A.「『漆喰の家=寒い』訳ではありませんが、その他の仕上げ材と同様の断熱工事が必要です。」
漆喰(消石灰)は多孔質構造なので断熱性があると思われがちですが、漆喰そのものに特段高い断熱効果はありません。
そのため、クロス仕上げや塗装の家と同様の断熱工事をご検討ください。
▶︎おすすめコラム:話題の“付加断熱”は果たしていいのか?メリット・デメリットを徹底解説
Q.「漆喰壁は地震の時にどうなる?」
A.「揺れ方や経年数によっては、ひび割れたりかけたりする可能性があります。」
漆喰壁は地震力の加わり方によって、ひび割れや欠けが発生するリスクがあります。
ただし、そのリスクはクロス仕上げや塗装と同等です。
また、漆喰は柔軟性がありセメントに比べて軽量なので、建物への荷重負荷を軽減でき、地震による影響を防げる側面もあります。
Q.「漆喰以外におすすめの塗り壁は?」
A.「自然由来の塗り壁材として、珪藻土やシラス壁も人気です。」
漆喰と同等かそれ以上の機能を持つ自然由来の塗り壁があります。
| 塗り壁材の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 珪藻土 | ・珪藻(海や湖に生息する植物性プランクトンの一種)の死がいが堆積して化石化した「二酸化ケイ素」が主成分 ・微細な多孔質構造で、漆喰と同様の機能を持つ ・単価目安は「3,000〜6,000円/㎡」と、漆喰よりリーズナブル |
| シラス | ・九州南部などの火山地帯で産出される火山灰「シラス」が主成分で、自然素材100%の塗り壁材 ・微細な多孔質構造で、漆喰と同様の機能を持つ ・単価目安は「6,000〜8,000円/㎡」 |
それぞれメーカーによって色合いや質感が異なりますので、現物サンプルを取り寄せて違いをご確認ください。
《家づくりのプロ》である私たち工務店と、《生活のプロ》であるお客様の知恵を融合し、「最高の家づくり」を目指します。

まとめ

漆喰には、室内環境の質を高めるメリットがある反面、事前に知っておいていただきたいデメリットや注意点もあります。
“漆喰の家”を建てたい方は、コストやメンテナンス方法、耐用年数(寿命)、デザイン性などを総合的に確認して検討する必要があります。
何十年も安心安全に住めるマイホームを建てたい方は、「土地選び・間取りのプラン・住宅性能」の全てにこだわりましょう。
デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、注文住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。